秘密のハグ
使用したAI Stable Diffusion XL年齢制限 全年齢
放課後職員室の片隅、夕方の空気が少し肌寒い。
紫峰怜花は、くしゃみをひとつ。
「風邪でしょうか」
声をかけてきたのは、帰り支度を終えた狭霧華蓮だった。
「んー、たぶん冷房のせいかも。大丈夫、気にしないで」
「……体温が低下すると免疫が落ちます。特に女性は冷えに弱い」
「そうね……ありがとう」
怜花が笑って受け流すと、華蓮は少しだけためらったあと、ポケットから小さなカイロを取り出した。
「これをどうぞ。まだほんのり温かいです」
「わ、ありがと……優しいのね、華蓮さんって」
「理にかなっているだけです。体温の保持には即効性があるので」
そう言いながらも、彼女は一歩だけ近づいた。何か言いたげな、でも躊躇うような目。
「……先生」
「なに?」
「ひとつ、実験をしてもいいでしょうか」
「実験?」
「はい。“ハグ”という行為が、心理的・生理的にどれほど体温に影響を及ぼすかの確認です」
「え、ちょっと待って、それって――」
言い終わらないうちに、華蓮はそっと腕を回してきた。
まるで羽のように軽い抱擁。でも、そこには確かな体温があった。
「……こうすると、オキシトシンが分泌され、副交感神経が優位になります。結果として、安心感が生まれ、身体が温まるのです」
「……へ、へぇ〜……詳しいのね……」
怜花の耳まで、じわりと熱くなる。
数秒後、華蓮は何事もなかったようにすっと離れた。
そして、ひと言。
「今のは実験です。正式な記録には含めません」
「……え……!?」
「でも、先生、顔色が少しよくなりました。……効果はあったようです」
そう言って、華蓮はふっと微笑んだ。どこか意地悪だけど、やさしい笑みだった。
「……もう、びっくりしたわ、ほんとに……」
怜花は頬を赤くしながら、カイロを握りしめた。けれど、もうそれに頼る必要はなかった。
放課後の空気はまだ冷たいけれど、胸の奥はほんのりとあたたかい。
そのぬくもりは、記録には残らないけれど、記憶にはきっと、長く残る。
秘密の記憶として……
紫峰怜花は、くしゃみをひとつ。
「風邪でしょうか」
声をかけてきたのは、帰り支度を終えた狭霧華蓮だった。
「んー、たぶん冷房のせいかも。大丈夫、気にしないで」
「……体温が低下すると免疫が落ちます。特に女性は冷えに弱い」
「そうね……ありがとう」
怜花が笑って受け流すと、華蓮は少しだけためらったあと、ポケットから小さなカイロを取り出した。
「これをどうぞ。まだほんのり温かいです」
「わ、ありがと……優しいのね、華蓮さんって」
「理にかなっているだけです。体温の保持には即効性があるので」
そう言いながらも、彼女は一歩だけ近づいた。何か言いたげな、でも躊躇うような目。
「……先生」
「なに?」
「ひとつ、実験をしてもいいでしょうか」
「実験?」
「はい。“ハグ”という行為が、心理的・生理的にどれほど体温に影響を及ぼすかの確認です」
「え、ちょっと待って、それって――」
言い終わらないうちに、華蓮はそっと腕を回してきた。
まるで羽のように軽い抱擁。でも、そこには確かな体温があった。
「……こうすると、オキシトシンが分泌され、副交感神経が優位になります。結果として、安心感が生まれ、身体が温まるのです」
「……へ、へぇ〜……詳しいのね……」
怜花の耳まで、じわりと熱くなる。
数秒後、華蓮は何事もなかったようにすっと離れた。
そして、ひと言。
「今のは実験です。正式な記録には含めません」
「……え……!?」
「でも、先生、顔色が少しよくなりました。……効果はあったようです」
そう言って、華蓮はふっと微笑んだ。どこか意地悪だけど、やさしい笑みだった。
「……もう、びっくりしたわ、ほんとに……」
怜花は頬を赤くしながら、カイロを握りしめた。けれど、もうそれに頼る必要はなかった。
放課後の空気はまだ冷たいけれど、胸の奥はほんのりとあたたかい。
そのぬくもりは、記録には残らないけれど、記憶にはきっと、長く残る。
秘密の記憶として……
プロンプト
なし
コメント
送信
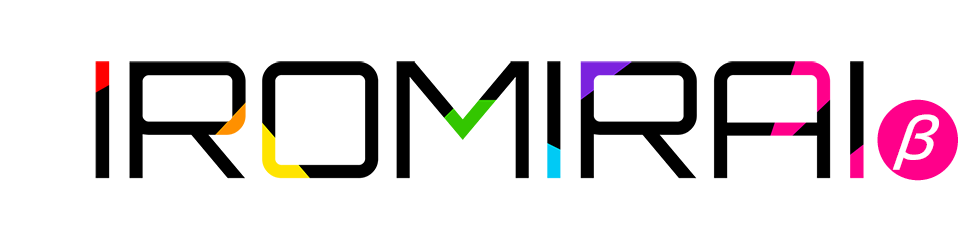








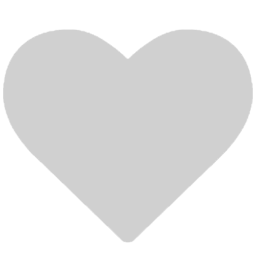 いいね
いいね




















